カタバミの種子飛散距離実験 ②(大成功の巻)
 |
「モンタ博士! 大失敗(だいしっぱい)って、どういうことですか。」 |
 |
「モンタ博士も考えがあまかったね。でも、そのおかげで正確(せいかく)な実験(じっけん)ができたね。」 |
 |
「失敗は成功(せいこう)のもとといいますね。」 |
 |
「そのとおりだね。カタバミの種が飛ぶといっても、せいぜい1mもいかないだろうと思ったのさ。それで、実験で使う鉢(はち)を真ん中において、そのまわりに白い紙をしいたのさ。」 |
 |
「それで、それで……。」 |
 |
「そしたら、何と、しいた紙の外までカタバミの種が飛んでしまったというわけさ。つまり実験1というわけさ。」 |
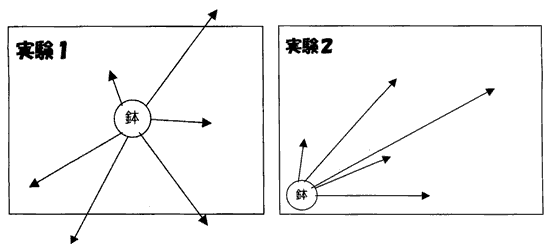 |
|
 |
「それで、それで……。」 |
 |
「そこで、実験2では、もう少し大きな紙を用意して、鉢を四角のはじっこに置くようにしたのさ。そうすれば、はみ出さないからね。どれだの数の種が飛んだかというよりも、どのくらいの距離(きょり)かの平均(へいきん)をみたかったから、この実験でもいいということさ。」 |
 |
「でも、実験1をやった結果(けっか)はどうだったんですか。」 |
 |
「全部で404この種が飛んだんだ。そして、平均を出したら約(やく)77cmくらい飛んだんだ。でも、紙の外に飛んだものもあるから、この結果は、正しい距離とは言えないね。」 |
 |
「そうですね。それで、実験2の結果はどうだったんですか。」 |
 |
「鉢の中に落ちた種もあるけど、それは数に入れないことにしたんだ。結果は、全部で1570この種が飛び、最高(さいこう)に飛んだものは、なんと2m94cm。平均約87cmということになったね。そして、20cmごとにどのくらいはじけて飛んだのかをグラフにまとめてみたんだよ。」 |
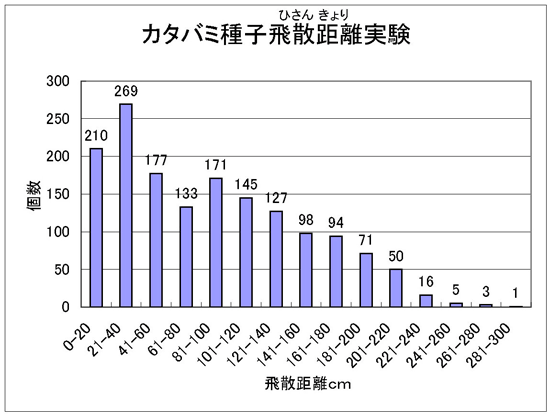 |
|
カタバミの高度な科学戦略いろいろ……
花には光を感じるセンサーのようなものが内蔵されているようで、光に合わせて活動するハチの生活リズムに合致しているらしい。また、3つのハート形の葉の合わせ部分には、水分を調整する組織があるようで、葉の自動開閉システムが働くようである。さらに、天に向かって立つその実はまさにロケット型で、種の発射装置のようだ。この種はそれぞれ、白い袋に包まれて大きくなる。最初は、袋は中に種と水分を入れたままで、風船のようにふくらんでいるが、種が大きくなるに従って、外側の細胞層の伸びは止まってしまい、内側の細胞層だけがなおも続けて伸びようと努力しているのである。そして、種が熟すと内側の細胞層は無理に押し縮められた状態になってしまう。すると、そんな時に、外側からの震動(風や雨などの震動)を与えると、次から次へと種が飛び出すのである。さらに、その種の表面には、瞬間接着剤も顔負けの透明な液体があり、それで、あちこちにはり付けられ、種をより遠くへと旅だたせるのである。おまけに、葉には蓚酸(しゅうさん)を含んでおり、体内のカルシウムイオンと結びつき、不溶解性の結晶にするなど、ケミカル的な防衛力もあるそうだ。
